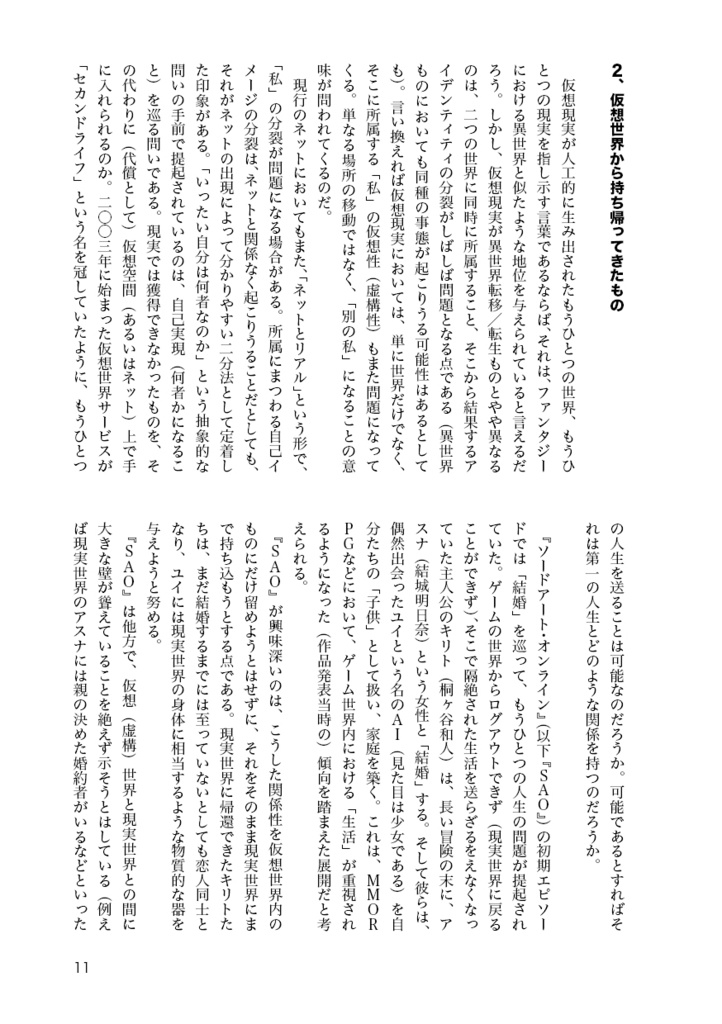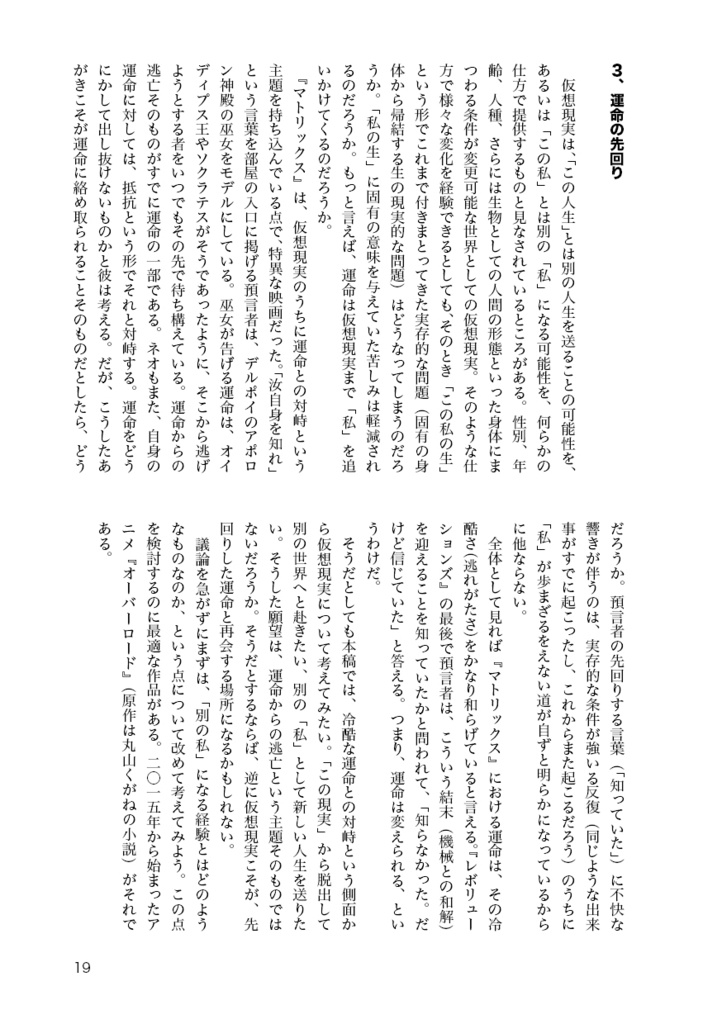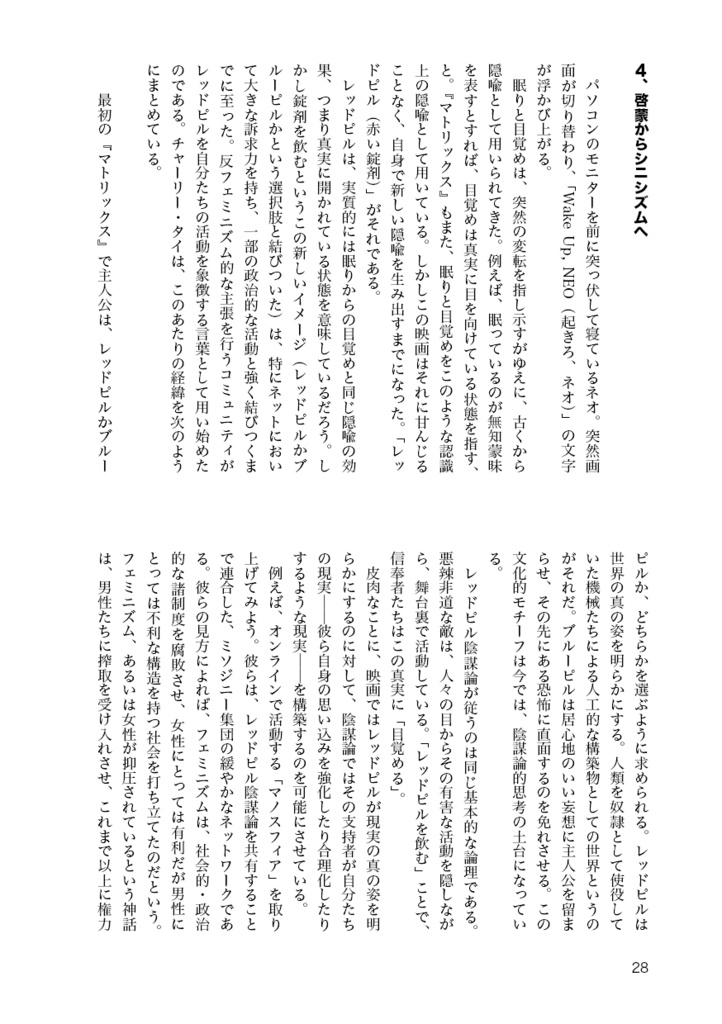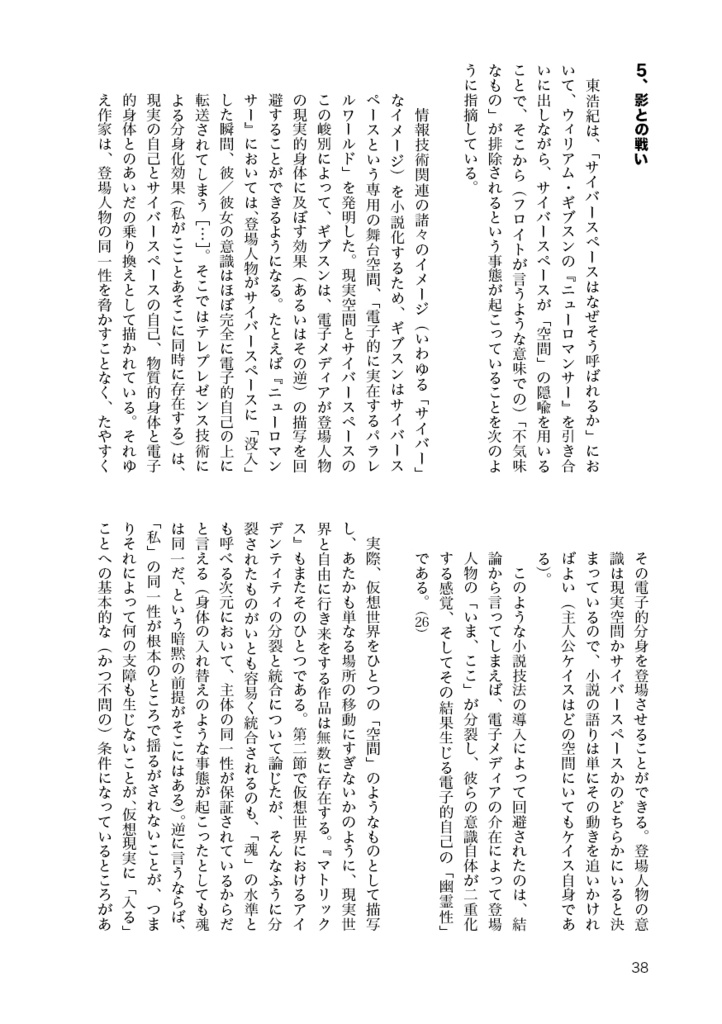マトリックス論——フィクションの仮想現実について
- 物販商品(自宅から発送)あんしんBOOTHパックで配送予定支払いから発送までの日数:7日以内在庫なし¥ 400
マトリックス論——フィクションの仮想現実について(志津史比古 著) (2022年11月20日発行、A5版、54ページ) 機械は人を騙すのだろうか。映画『マトリックス』が仮想現実に対して提起しているのは、まずこのような問いである。この問いが十全な意味を持つためには、騙すという行為についてよく考えてみる必要がある。とりわけ、誰かから騙されるというのではなく、人は時に自分で自分を騙そうとするという傾向性についてよく考えてみなければならない。 『マトリックス』の与えた鮮烈なイメージとは、レッドピルを飲むことによって生じる脱出の感覚、つまり「この現実」の外に出るという感覚である。「ここ」で生きるのをやめて、「ここではないどこか」に行くことができる、あるいは「この私」ではない「私」になることができる。そうした希望があの映画で示されていたのではないだろうか。仮想現実が単なる情報環境として捉え返されるならば、そうした希望は縮減してしまうのではないだろうか。 仮想現実は発展途上の技術である。「メタバース」という言葉を巡る昨今の過熱した状況も、「未来」の名の下に「現実」を括弧に入れることができるがゆえに――この空白から無数の空想を引き出せるがゆえに――引き起こされた事態という印象を抱く。仮想現実を描いてきたフィクションは、具体的かつ詳細なイメージを提供してきたという点で、そうした過剰な期待を醸成する役割を果たしてきただろう。 「新しい技術」という見かけの下に提示されている事柄が、実際は、より古いものから借り受けられた多くのものから出来上がっている場合がしばしばありうる。仮にそれが古い問題であったとしても、その提起のされ方のうちに何か新しいものが見つかるかもしれない。仮想現実を夢想することよってわれわれは、どのような現代的な問いを提起しようとしているのだろうか。